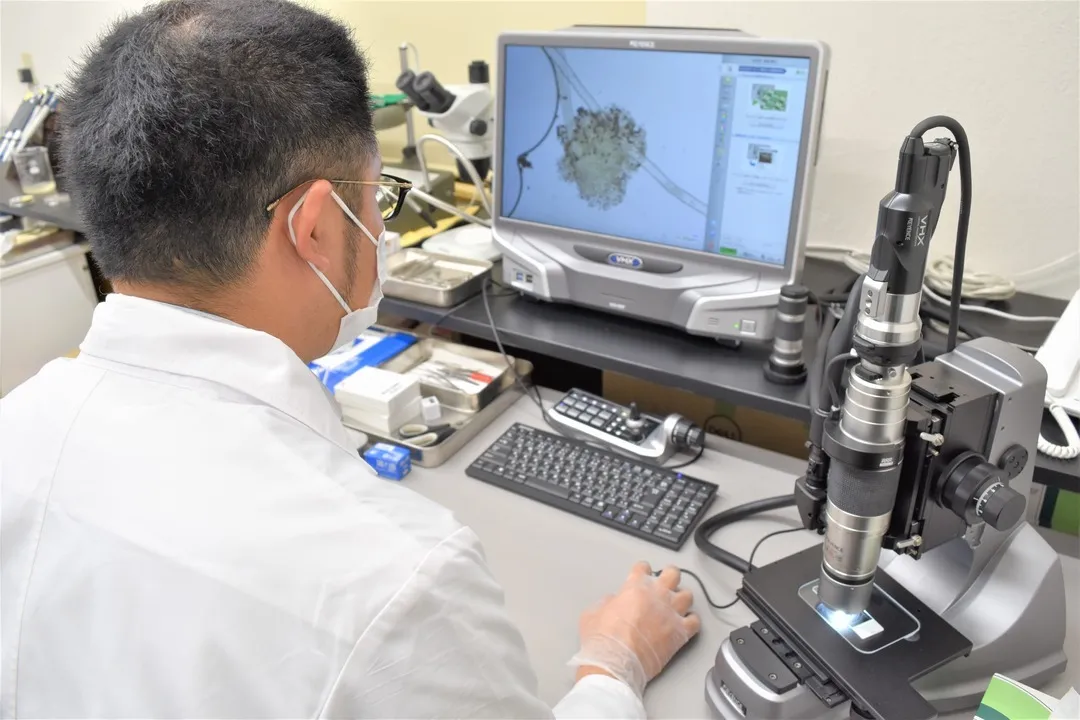「中古住宅や賃貸がカビ臭い!」原因とスッキリ消臭&除去法をプロ解説
2025/03/27
中古住宅や賃貸で部屋がカビ臭い!?原因から対策まで徹底ガイド
この記事でわかること
●カビ臭い家の主な原因と発生しやすい場所
●カビ臭がもたらす健康リスクと影響
●カビ臭のチェックポイントと簡単なセルフ診断法
●消臭剤や換気など一時的な対処法とその限界
●素材・場所別の本格的なカビ除去方法と施工事例(MIST工法の紹介)
●専門業者に依頼すべきタイミングとそのメリット
●カビ再発を防ぐための将来的な予防策
中古の家を購入しようと内見したとき、「なんだか部屋がカビ臭い…」と感じたことはありませんか?あるいは賃貸暮らしで部屋のカビ臭さに悩んでいたり、リフォーム現場でカビ臭対策に頭を抱えている方もいるでしょう。カビ臭い家は不快なだけでなく、健康や建物にも悪影響を及ぼしかねません。本記事では、「カビ臭い家」の原因から対策までを徹底解説します。原因を知り、正しく対処すれば、嫌なカビのニオイとおさらばできます。中古住宅の購入を検討中の方、賃貸住まいでカビ臭に困っている方、そしてリフォーム業者の方も、ぜひ参考にしてください。実例としてカビ対策専門業者 カビバスターズ福岡 の施工事例や独自技術である MIST工法 も紹介しますので、プロの視点からのアドバイスも要チェックです。それでは、カビ臭の原因と対策を順番に見ていきましょう。
目次
カビ臭さの主な原因とは?
部屋がカビ臭くなる背後には、いくつかの典型的な原因があります。まず大前提としてカビ(真菌類)が繁殖すると、その代謝物や胞子によって独特の「カビ臭」が発生します。カビは湿度の高い環境を好み、湿気がこもって換気が不足した空間で増殖しやすいため、建物内の湿気と換気不足が最大の原因です。例えば梅雨時や夏場など湿度が高い季節に、長時間締め切ったままの部屋では空気中の水分が増え、壁紙や木材に染み込んでカビが発生しやすくなります。また経年劣化による建物の不具合も見逃せません。築年数が経った住宅では、屋根や外壁の防水劣化で雨漏りが起きたり、断熱不足で壁や窓に結露が発生したりします。そうした水分が建材に染み込むことでカビの温床となり、悪臭の原因となるのです。
換気設備の有無も重要なポイントです。2003年に建築基準法が改正される以前の住宅では24時間換気システムが義務化されておらず、古い家ほど換気不良になりがちです。その結果、湿気がこもってカビ臭が発生しやすくなります。逆に近年のリフォームで気密性が上がった住宅でも、換気計画が不十分だと「乾燥不足」でカビが増える事例があります。つまり、高気密高断熱化に伴って意識的な換気が行われないと、かえってカビには好都合の環境になるのです。
湿気がこもった古い家の壁にカビが発生し黒ずんでいる様子。こうした場所から嫌なカビ臭が漂うことが多い。湿度や水漏れが原因で壁材にカビが繁殖すると、クロスの裏まで根を張り、表面を清掃しても臭いが残ることもある。
さらに、「カビ臭い」と感じるニオイの原因が実はカビ以外の場合もあります。指摘のように、建材に使われている古い接着剤や防腐剤が劣化して悪臭を放っているケースです。とくに中古住宅では、床下や壁内部で使われた薬剤の臭いがカビ臭に似ていることがあります。このようにニオイの発生源がカビなのか別の物質なのかを見極めることも大切です。カビでない場合はカビ取り剤では解決できず、別の対応が必要になるためです。いずれにせよ、「湿気」「換気不足」「建材劣化」がカビ臭発生の三大原因と言えるでしょう。
カビ臭がもたらす健康リスク
カビ臭い環境に長く身を置くことは、私たちの健康にも影響を与えかねません。カビそのものは目に見えなくても胞子や揮発性の代謝産物が空気中に漂い、それらを吸い込むことで様々な健康リスクが生じます。
まず挙げられるのがアレルギー疾患の悪化です。空気中のカビ胞子を吸い込むと免疫系が過敏に反応し、アレルギー性鼻炎や喘息(ぜんそく)、アトピー性皮膚炎などの症状を誘発・増悪させます。たとえばカビが多い部屋で寝起きしていると、くしゃみや鼻水、咳が止まらなくなったり、肌のかゆみや湿疹がひどくなったりすることがあります。実際に「部屋がカビだらけで寝ていたら鼻炎や喘息が悪化した」という報告も珍しくありません。
次に感染症のリスクも見逃せません。通常健康な人では稀ですが、免疫力の低下した方や肺の持病がある方がカビ汚染された空気を吸い続けると、肺にカビが感染して「真菌症」を引き起こす場合があります。代表的なのはアスペルギルス症で、カビ( Aspergillus 属)の胞子が肺に入り込み増殖してしまう病気です。免疫不全の方や高齢者では重篤化する恐れもあるため注意が必要です。また日本特有のものとして、夏場のエアコン内部のカビが原因で起こる「夏型過敏性肺炎」といった過敏症(アレルギー性肺炎)を発症するケースも知られています。長引く夏風邪のような咳や微熱がある場合、住環境のカビが原因となっている可能性も考えましょう。
さらに、カビ臭が充満した室内ではシックハウス症候群の症状が出ることもあります。カビ由来の有機化合物や胞子で空気が汚染されることで、頭痛・めまい・倦怠感(だるさ)などを訴える人もいます。シックハウス症候群というとホルムアルデヒドなど化学物質を思い浮かべがちですが、カビも原因の一つになり得ます。慢性的にカビ臭い部屋にいることで知らず知らず体調不良になるケースもあるのです。
このように、カビ臭は単なる臭いの問題にとどまらずアレルギー・呼吸器系への悪影響や体調不良につながります。特に小さなお子さんや高齢者、アレルギー体質の方がいるご家庭では、早急に対策することが大切です。「たかがカビ臭」と侮らず、健康リスクを十分認識しておきましょう。
カビ臭のチェックポイントとセルフ診断法
では、自分の家がカビ臭いと感じたとき、まず何をすべきでしょうか?ここではカビ臭の原因箇所を突き止めるためのチェックポイントと、簡単にできるセルフ診断の方法を紹介します。
臭いの種類を確かめる: 最初に、その臭いが本当にカビ由来かを見極めましょう。前述の通り、カビ臭は土埃のような「湿った土臭さ」を感じるのが特徴で、一方で雑菌が原因の臭いは生ゴミのような酸っぱい臭いになると言われます。もし臭いの質が明らかに下水臭やケミカルな刺激臭であれば、カビではなく排水口の臭気や化学物質の可能性があります。まずは臭いの感じをメモし、カビ特有の匂いかどうかを判断材料にしましょう。
発生源を探す: 次に、家の中で臭いが強く感じられる場所を探ります。カビ臭がする場所は実に様々ですが、特に風通しが悪く湿気の溜まりやすい所を重点的にチェックします。例えば以下のようなポイントは要注意です:
●押入れやクローゼットの中(壁の隅や天井にカビがないか)
●キッチンのシンク下収納や食品庫(湿気と食品残渣でカビ繁殖しやすい)
●浴室や脱衣所(エプロン内部や換気扇内部のカビ)
●洗濯機周り(防水パンや排水口付近のカビ)
●窓際のカーテンやサッシまわり(結露によりカビが発生)
●エアコン内部(フィルターや送風ファンにカビが生えて臭う)
●カーペット敷きの床や畳の裏側(見えない所でカビ繁殖していないか)
●地下室や床下収納、天井裏(普段目にしない空間のカビ臭漏れ)
こうした場所を順番に目視と嗅覚で確認しましょう。懐中電灯を使って隅々まで見たり、床に膝をついて鼻を近づけて臭いを嗅いでみるのも有効です。「この辺りが一番臭う」という場所が見つかれば、その近くにカビ源が潜んでいる可能性が高まります。
見えないカビを推測する: 表面上カビが見当たらない場合でも油断はできません。壁紙(クロス)の表面は綺麗でも、裏の石膏ボードや断熱材がカビていることがあります。畳やフローリングの下地、天井板の裏側など表から見えない部分で繁殖しているケースも多いのです。特に押入れの背面壁や床下は発見が難しいポイントです。住まい全体でカビ臭が消えないときは、床下や天井裏でカビが広がっていないか疑ってみましょう。
セルフ診断の一つの目安として、「部屋を閉め切って数時間後に入室した際、カビ臭が強いかどうか」を試す方法があります。換気後しばらく締め切り状態にし、その後ドアを開けた瞬間の空気を嗅いでみて、モワッとカビ臭が感じられれば何らかの発生源が残っている証拠です。発生源が特定できない場合は無理せず次に述べる専門業者への相談も検討しましょう。
消臭剤や換気など一時的な対処法とその限界
カビ臭に気付いたらすぐにでも臭いを消したいもの。ここでは応急処置的にできる一時的な対処法をいくつか紹介します。ただし根本解決にはならない場合が多いため、その限界も合わせて押さえておきましょう。
(1) 消臭剤の設置: 市販の消臭剤(置き型・スプレー式)を使う方法です。部屋用の消臭剤にはカビ臭に効果的な成分を含むものもあり、臭いを一時的にマスキング(覆い隠す)したり吸着して軽減してくれます。手軽で費用も安く済むメリットがあります。ただし消臭剤はあくまで臭いに対処するもので、カビそのものを除去するわけではない点に注意が必要です。消臭剤で臭いが和らいでも、カビ自体が生きていればまたすぐに臭いは戻ってきます。また空間全体の強いカビ臭には焼け石に水なことも多いでしょう。
(2) 換気と乾燥: 窓を開け放って空気を入れ替える、換気扇を回す、サーキュレーターや扇風機で風を通す、といった徹底換気も即効性があります。こもったカビ臭を屋外に逃がし、新鮮な空気と入れ替えることで臭気はかなり薄まります。ただしこれも根源的解決ではありません。換気している間は良いのですが、閉め切ればまた臭う可能性があります。晴れた日の日中に部屋を開放して湿気を飛ばすこと自体はカビ抑制に有効なので、習慣としては◎ですが、既に発生したカビには換気だけでは不十分です。
(3) エアコン・空気清浄機の活用: エアコンのドライ運転(除湿機能)で室内の湿度を下げれば、カビ臭も感じにくくなります。また空気清浄機を使うと、臭い成分の分解フィルターや活性炭フィルターが臭気を除去し、さらにフィルターが空気中のカビ胞子を捕集してくれます。空気清浄機は消臭剤より高価ですが、臭いの軽減効果が高く、カビ胞子対策にもなる点で優れています。とはいえ、やはりこれらも補助的な対策に過ぎません。エアコン内部にカビがある場合は運転すると逆に臭いが広がることもあるため、フィルター清掃や内部クリーニングも必要です。
以上のような一時対策を組み合わせれば、一定期間はカビ臭を和らげることができます。「今すぐ来客があるので応急処置したい」といった場合には有効でしょう。しかし繰り返しになりますが、臭いの元であるカビそのものを除去・退治しない限り根本的な解決にはなりません。消臭剤や換気でしのぎつつも、並行して次章で述べる本格的なカビ除去に取り組むことをおすすめします。
本格的なカビ除去方法 – 素材別・施工箇所別の対処
カビ臭の原因がカビである以上、発生源のカビを除去することが最重要課題です。ここでは住宅内の代表的な場所・素材ごとの本格的なカビ取り方法を解説します。軽微なカビであればご自身で対応可能な場合もありますが、広範囲に及ぶ場合は無理をせず専門業者に任せる判断も必要です。
壁・天井のカビ除去
壁紙クロスや塗り壁、天井板に発生したカビは見た目にもショックなものです。まず表面に黒カビ(黒い斑点状)が見える場合は、市販のカビ取り剤(塩素系漂白剤やアルコール系)を使って清掃します。ゴム手袋とマスク、保護メガネを着用し、カビ部分にスプレーしてしばらく置いた後、擦らずに布で押さえるように拭き取ります。塩素系薬剤ならカビの色素も漂白できます。ただし漂白剤は素材の色まで落とすリスクがあるので、壁紙の種類によっては注意が必要です。また、強い薬剤でゴシゴシ擦ると壁紙や下地を傷めてしまい、そこに凹凸ができると新たなカビが生えやすくなるという指摘もあります。そのため、なるべく素材を傷めずにカビだけを殺菌・除去することが理想です。
表面を拭き取った後、カビの根が残っていないか確認します。クロス表面のカビは取れても、石膏ボード内部まで菌糸が入り込んでいると再発しやすいためです。臭いがまだ残る場合は内部にカビが残存している可能性が高く、思い切って壁紙を剥がして下地を消毒する、場合によっては石膏ボードごと交換するといった対策が必要になることもあります。天井の場合も同様で、表面のカビを落とした後に天井裏の状態を確認しましょう。天井裏の断熱材がカビていた例もあります。
天井や高所のカビ取り作業は脚立や道具が必要で危険も伴います。洗剤が目に入る事故も起こりかねません。天井全面に広がったカビなど手に負えない場合は専門業者に任せることを検討してください。無理な作業より安全と確実性が優先です。
床・畳のカビ除去
フローリング表面にポツポツと出たカビは中性洗剤やアルコールで拭き取れば落ちることが多いです。その後しっかり乾燥させ、必要に応じて木部用の防カビ剤を塗布しておくと良いでしょう。問題は床下地やカーペット、畳などの見えない部分のカビです。
畳に生える白カビは梅雨時などによく見られます。表面がうっすら白く粉を吹いたようになるのが特徴で、これもアルコールや酢水を含ませた雑巾で拭けば除去できます。ただ畳表の内部や裏側にまで及ぶと個人で完全に除去するのは難しく、畳店に依頼して表替え(ござ部分の張替え)を検討することになります。カーペットの場合、下に敷いているウレタンマットや床下地までカビが達していると、表面を掃除してもまたすぐに臭ってきます。この場合はカーペットそのものの交換が必要かもしれません。
床下収納や点検口があるなら、一度開けて床下の湿気とカビ状況を確認してみましょう。床下がジメジメしてカビ臭が上がってきている場合、床下換気扇の設置や防湿シート敷き、防カビ剤の散布など専門的な対策が必要になることもあります。床下のカビは家全体のカビ臭につながる重大なポイントなので、見逃さないよう注意してください。
押入れ・家具のカビ除去
押入れやクローゼットの中はカビ臭の発生源になりやすい場所です。収納内部でカビ臭がする場合、まず中の物をすべて出して確認しましょう。壁や天井、床にカビが生えていないか、収納していた衣類や布団にカビ斑点や異臭がないか調べます。木製の棚板や引き出しにもカビが発生しがちです。見つけたカビはアルコールで拭き取り、乾燥させます。収納物も、カビ臭が染みついているようなら天日干しか洗濯・クリーニングしましょう。
家具(タンスや本棚など)の裏面と壁との隙間も盲点です。家具を動かして裏側の壁を点検し、カビがあれば清掃します。家具自体の背板がカビていたら、こちらも清掃し、可能なら防カビスプレーを吹き付けておきます。再発防止のためには押入れやクローゼットにすのこを敷いて床との隙間を作る、時々扉を開放して換気する、除湿剤を置く、といった工夫も有効です。
浴室・水まわりのカビ除去
浴室や洗面所、キッチンシンク下など水まわりのカビは、臭いのみならず衛生面からも早期対応が必要です。浴室のゴムパッキンやタイル目地に発生した黒カビは塩素系カビ取り剤の出番です。ジェルタイプの漂白剤を塗布し、一定時間おいてから洗い流すとかなり綺麗になります。換気扇内部にホコリとカビが溜まっていると、スイッチON時にカビ臭を撒き散らすので分解清掃をしましょう(難しければ業者に依頼)。キッチン下の収納では、水漏れや結露で板材がカビていないか確認します。消毒用エタノールなどで拭き取ればOKですが、配管からの漏水が原因の場合は修理を先に行わないと再発します。
エアコン内部のカビについても触れておきます。エアコンをつけるとカビ臭い風が出る場合、熱交換器フィンや送風ファンにカビが生えている可能性大です。市販のエアコン用洗浄スプレーもありますが、奥の送風路までカビを除去するのは難しく、完全に臭いを取るには専門のエアコンクリーニング業者に依頼するのが確実です。内部まで高圧洗浄し、防カビコートをしてくれる業者を選べば、臭いの元から断てるでしょう。エアコンのカビを甘く見ると部屋中に胞子をばら撒くことになるので注意してください。
以上、場所や素材別にカビ取りのポイントを述べました。DIYで対処できるカビは早めに除去し、防カビ処置まで行うことが肝心です。ただし、広範囲に及ぶカビや構造内部のカビについては、無理に自分で何とかしようとすると安全面・効果の面で限界があります。次の章で紹介する専門業者の力も視野に入れ、適切に対処しましょう。
カビバスターズ福岡の施工事例紹介 – MIST工法で徹底除カビ
ここで、実際にプロの手でカビ臭の問題を解決した施工事例を紹介します。福岡を拠点にカビ取り専門サービスを提供している「カビバスターズ福岡」の事例で、独自開発の MIST工法 によるカビ除去技術が活躍しました。
●築30年木造住宅のカビ臭トラブル解決
福岡市内の築30年超の中古戸建てを購入したAさん一家は、入居当初から家全体のカビ臭に悩まされていました。特に押入れと寝室の天井付近から強いカビ臭がし、家族に喘息持ちのお子さんがいることもあって心配に…。Aさんは市販の消臭剤を置いたり、自分で見えるカビを拭き取ったり試みましたが、臭いは一向に改善しません。そこで専門業者であるカビバスターズ福岡に調査と除カビを依頼しました。
業者のスタッフが家中を徹底調査したところ、原因は二つ判明しました。一つは押入れの壁内部です。押入れ背面のベニヤ板の裏側一面に白カビが発生しており、これが臭気を放っていました。もう一つは寝室天井裏の断熱材です。築年数による小さな雨漏りが起きており、湿ったグラスウール断熱材に黒カビが繁殖していたのです。目に見えない部分でしたが、専門業者は真菌検査や機材を用いてカビの存在範囲を可視化し、原因箇所を特定しました。
天井裏まで広がった深刻なカビ汚染の様子。天井表面にシミ状のカビが確認できる。このようなケースでは内部に根を張ったカビを徹底的に死滅させる必要がある。MIST工法によるミスト噴霧なら、天井裏の見えない菌糸まで行き渡り、安全に除去が可能。
カビバスターズ福岡は早速これらの箇所に対し、独自のMIST工法で除カビ施工を実施しました。MIST工法とは、カビバスターズが開発した特殊な工法で、素材に応じた専用の殺菌液をミスト状に噴霧し、カビを菌糸レベルから根こそぎ死滅させる技術です。特徴は「削らない・擦らない・酸を使わない」処方で、建材を傷めずに安全にカビを除去できる点にあります。実際今回も、押入れ壁を剥がすことなく隙間からミスト薬剤を充満させることで、裏側のカビまでしっかり行き渡らせました。天井裏にも小さな穴を開けてノズルを差し込み、断熱材ごとカビ菌を処理しました。
噴霧後、殺菌液が乾燥するのを待ってから、防カビコーティング剤も施工されています。施工全体は半日ほどで完了し、家中に漂っていたカビ臭は施工直後からほとんど感じられなくなりました。数日換気した後、Aさんご一家に引き渡されましたが、その後数ヶ月経ってもカビ臭の再発は無く、喘息のお子さんの症状も改善傾向とのことです。「リフォームで壁紙を全部張り替えないと無理かも」と覚悟していたAさんは、解体なしでここまで臭いが取れるとは思わなかったと大変驚き、専門業者の技術力に感謝されました。
● MIST工法の技術解説とメリット
今述べた事例でも登場したMIST工法について、もう少し詳しく解説します。MIST工法はカビバスターズの登録商標であり、同社が長年の研究で開発した建物カビ改善システムです。にあるように、従来のカビ取りがブラシで擦ったり塩素で漂白したりと素材へのダメージを伴うのに対し、MIST工法では素材に合わせて調合した専用の薬剤を霧状に吹き付けるため素材を傷めません。木材や和紙といったデリケートな素材にも適用でき、文化財レベルの古い建材でも綺麗にカビだけを除去できる実績があります。また、薬剤には人体や環境に優しい成分を用いており、小さなお子様やペットがいる家でも安心して施工できるのもメリットです。
施工手順としては、まず現地調査とカビの種類・範囲の検査を行い(必要に応じて専門機関の真菌検査も実施)、最適な薬剤を選定します。その後、対象箇所に噴霧器でミストを行き渡らせ、一定時間反応させてカビ菌を不活化します。最後に換気乾燥させ、防カビ剤でコーティングして終了です。場合によっては施工前後でカビの菌数測定を行い、しっかり除去できたことをデータで示すこともあります。まさに見えないカビを「見える化」して原因を突き止め、根こそぎ退治して再発防止まで施す包括的なサービスと言えるでしょう。
このような最新技術を駆使すれば、頑固なカビ臭問題も解決できる可能性が高いです。自力ではどうにもならないレベルのカビ臭に悩んだら、MIST工法を持つ専門業者への相談を検討してみてください。
専門業者に依頼すべきタイミングとメリット
カビ臭対策について、ここまでセルフチェックや自分でできる除去法、そしてプロの技術を紹介してきました。では実際問題、どのタイミングで専門業者に頼るべきか?迷うところですよね。一般的に以下のような状況では、業者への依頼を検討することをおすすめします。
●家全体が常にカビ臭い:一部屋だけでなく家中どこにいてもカビ臭を感じる場合、床下や天井裏など構造全体にカビが広がっている可能性があります。個人で原因を突き止めるのは困難なので、早めにプロの調査を依頼しましょう。
●広範囲にカビが発生:壁一面、天井一帯、床下全面など、自力清掃が追いつかない規模のカビは業者の出番です。無理に漂白剤で部屋中やると刺激臭で体調を崩す恐れもありますし、施工のプロに任せた方が安全確実です。
●何度掃除しても再発する:自分でカビを拭き取ってもすぐにまた臭ってくる・生えてくる場合、根本原因が除去できていません。プロなら隠れた原因箇所まで探し出し、再発防止策までセットで行ってくれます。
●健康被害が出始めている:家族にアレルギー症状や咳が出る人がいる、カビ臭で気分が悪くなる等の状況ならば、悠長に構えていられません。健康を守るためにも専門的な除カビ処置を急ぐべきです。
●中古住宅購入前の点検:購入を検討している中古物件でカビ臭がしたりカビ跡がある場合、契約前に業者に調査してもらうのも一つの手です。後になって大規模なカビ問題が見つかるリスクを減らせます。
専門業者に依頼するメリットは何と言ってもその徹底調査と確実なカビ除去にあります。プロは豊富な経験と機材を駆使して、素人では気づけない原因を暴き出します。のように、専門の真菌検査や機器で家の隅々までチェックし、カビの存在箇所を科学的に突き止めてくれます。また、適切な薬剤選択や施工法により家と人体に優しい方法でカビを根絶してくれます。作業中に出るカビ臭や有害物質も業者なら防護しながら進めるので安心です。
さらに、業者によっては施工後にカビ再発保証や定期点検サービスを提供していることもあります。一度プロに任せればそれで終わりではなく、アフターフォローでカビの再発防止を手伝ってくれるのです。費用は掛かりますが、「長い目で見れば家族の健康と家を守る投資」と考えると決して高い買い物ではないでしょう。実際、カビによる建材劣化を放置して後でリフォーム費用が嵩むより、早期にプロ対策しておいた方が安く済むケースも多いです。
最後に、業者選びのポイントとしては「カビ取り専門の実績があること」「自社でカビ検査や再発防止策まで行ってくれること」「使用薬剤や工法が安全であること」などをチェックすると良いでしょう。今回例に挙げたカビバスターズ福岡のように、専門知識と独自技術を持つ業者なら安心です。相談や見積もりは無料のところも多いので、困ったら一人で悩まずプロに問い合わせてみてください。
カビ臭再発を防ぐ!将来的な予防策
せっかくカビ臭を解消しても、また同じことを繰り返しては意味がありません。将来的な再発防止策もしっかり講じて、カビ臭と無縁の快適な住まいを維持しましょう。
● 徹底した湿度管理: カビ予防の基本は湿度コントロールです。室内の湿度がだいたい50~60%以下に保てるよう意識しましょう。梅雨時や夏場は除湿機やエアコンのドライ機能を活用して湿度を下げます。特に留守がちな家や空き家では、晴れ間に定期的に除湿機を稼働させるなど工夫してください。押入れ・クローゼット内には市販の除湿剤や調湿シートを置いておくと効果的です。観葉植物の水やり過多や、加湿器の使いすぎにも注意し、必要以上に湿度を上げない生活を心がけます。
● 定期的な換気: 新築・中古を問わず、現代の住宅は気密性が高くなっています。24時間換気システムがある場合は必ず稼働させ、フィルター清掃も怠らずに。換気扇だけに頼らず、窓を開ける自然換気も組み合わせましょう。特に料理や入浴の後は湿気がこもりやすいので、その都度しっかり換気して湿気を追い出します。家具配置も工夫し、壁にベタ付けせず少し隙間をあけて空気が流れるようにするとカビ発生抑制につながります。
● 断熱・気密の見直し: 実は断熱不足による結露もカビの大敵です。冬場に窓や壁が結露してびしょびしょ…という家は要注意。結露はそのままカビの養分になりますから、発生させない工夫が必要です。二重サッシや断熱窓へのリフォーム、壁の断熱材追加などで室内外の温度差を小さくすれば結露が減り、カビ予防になります。また逆に気密性が高すぎて湿気が抜けない家では、適切な調湿換気システムの導入を検討しても良いでしょう。要は「断熱して結露させない」「換気して湿度を下げる」のバランスが大事です。
● 防カビ仕様への工夫: リフォームや模様替えの機会には、防カビ性能の高い建材や塗料を選ぶのも有効です。防カビ剤入りのクロス糊や塗装剤、調湿機能のある珪藻土クロスなど、市販品にも色々あります。浴室なら防カビ仕様のシーリング材に打ち替える、キッチンや洗面所はカビが付きにくいパネル材を貼るなど、カビに強い環境づくりを意識しましょう。また、カビが発生しやすい梅雨前には一斉に掃除と除菌を行うなど、季節に応じた予防メンテナンスも効果があります。
● 定期点検とプロの活用: 年に一度は家の隅々を点検し、怪しいカビ臭やシミを見つけたら早期に対処しましょう。自力で対処が不安な場合は、早めにプロに相談して簡易調査を依頼するのも手です。カビバスターズ福岡など専門業者では、カビ予防のアドバイスも含めたサービスを提供していることがあります。定期的に空気中のカビ菌数を測定してもらうなど、プロと二人三脚で家を健康に保つのも賢い選択と言えます。
まとめ
以上、「カビ臭い家」の原因から対策・予防までを総合的に解説してきました。カビ臭さは放っておくと生活の質を下げるだけでなく、知らず知らず健康被害や資産価値の低下を招く怖れがあります。しかし原因を正しく突き止め、適切な方法で除去し、その後再発を防ぐ工夫をすれば必ず改善できます。「ちょっと面倒だな…」と思うかもしれませんが、快適で安心して暮らせる住まいを取り戻すためにひと手間かけてみましょう。もし自力では難しい場合は、遠慮なく専門のカビ対策業者に頼ってください。プロの力を借りれば、頑固なカビ臭ともサヨナラできるはずです。住まいのカビ臭トラブルを解決し、清潔で心地よい空間を取り戻しましょう!
----------------------------------------------------------------------
稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県
カビバスターズ福岡
〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14
電話番号 : 090-8159-7525
【検査機関】
一般社団法人微生物対策協会
----------------------------------------------------------------------